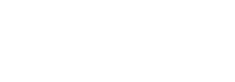「AIに関連する資格の最高峰」として、注目を集めるE資格。新しい時代に必要とされるAIエンジニアを目指す人にとっては、取っておきたい資格の一つです。
E資格試験は試験そのものの難易度が高く、合格を勝ち取るためにはそれなりの準備期間が必要です。今回は、準備期間を経て、いよいよ臨む試験日当日について解説します。
E資格とは?
まず、これからE資格試験の受験を検討する人のために、E資格はどのような資格か解説します。
E資格はAIエンジニアのための資格
E資格は、正式名称をJDLA Deep Learning for ENGINEER(JDLAディープラーニングフォーエンジニア)といいます。
JDLAとは、一般社団法人日本ディープラーニング協会の略称であり、E資格はこのJDLAによって創設されました。JDLA設立の目的はディープラーニング技術を向上させ、日本の産業競争力の向上を目指すことです。
JDLAはE資格のほかに、AIに関する基本的かつ広い知識を問う「G(ジェネラリスト)検定」を実施しています。AIの基礎的な知識を得るためのG検定に対して、E資格は、高度な理論の理解と実装のための知識を問う内容となっています。
E資格に合格するとどのようなスキルが身に付く?
E資格は、「ディープラーニングの理論を理解し、適切な手法を選択して実装する能力や知識を有するAIエンジニア」を目指すための資格です。
近年では、産業分野におけるディープラーニング技術の活用が進み、高度な知識がなくてもAIが実装できるフレームワークなども登場しています。基礎的な画像認識AIであれば、企業のいち担当者でも実装できる場合もあります。
しかし、E資格試験で求められるのは、ディープラーニング技術のさらに深い領域における知見です。AIの動きを理論や計算式レベルまで理解し、Pythonを使用した実装までできる知識が要求されます。
ここまで深くAIの知識を問う資格試験は世界的にも珍しく、E資格の取得は、AIエンジニアとしての知識を確固たるものにできます。
さまざまな業界でAI技術をどのように活かしていくのか、どのように不可能を可能にするのかといった「革新的な挑戦」において、先陣を切って挑む人材になれるといっても過言ではありません。
E資格試験の受験者数や合格率は?
E資格試験が初めて実施されたのは2018年であり、比較的新しい資格です。
しかし、E資格試験の合格は、高度なAI人材であることの証明でもあるため、すでに資格としての価値は広く認められています。さまざまな業界が、E資格合格者に熱い視線を注いでいるといって良いでしょう。
E資格の受験者数は、開始当初は300人台でしたが、近年では毎回850人ほどが挑戦しています。それだけE資格が実践的な価値を持つ資格として認知されてきたということでしょう。
2023年8月25日(金)、26日(土)、27日(日)に実施された「2023#2」では、受験者数1,065名のうち合格者は729であり、合格率は68.745%という結果でした。
近年では合格率は、70%を超える年が続いており、しっかりと準備して試験に臨む人の数が増えていると考えられます。効率的な勉強法や質の高い試験対策講座が増えてきたことも合格率の高さにつながっているかもしれません。
E資格の合格率はなぜ高い?難易度は?
E資格は合格率が7割を超えることから、それほど難しくない試験だと勘違いする人が少なくありません。
しかし、国内におけるディープラーニング関連の資格試験としては最高難易度であることは間違いなく、「IPA・情報処理試験レベル3、4」(最近ではほぼレベル4)と同等の難しさといわれています。
そもそもE資格試験を受験するためには「過去2年以内にJDLA認定プログラムの受講を修了していること」という条件をクリアしなければなりません。
JDLA認定プログラムは、それ自体がかなりハイレベルな内容になっており、たとえエンジニアとして活躍している人であっても、AIや数学の知識が少ない場合はすぐに理解できる内容ではないでしょう。
つまり、E資格の受験者であるということは、JDLA認定プログラムを修了できるだけの実力を持った人ということになります。これが、高い難易度の割に合格率が高い理由といって良いでしょう。
試験勉強を実際に開始すると、そんなに簡単に合格できる資格でないことがよくわかるはずです。
試験当日までに知っておきたい、E資格試験はどんな試験?

すべての資格試験がそうであるように、事前に試験当日の様子をイメージすることで、緊張感が低減し、気持ちが安定します。ここでは、E資格試験がどのような試験なのか、試験当日がイメージできるよう具体的に紹介します。
E資格試験の試験概要
2022年12月現在、JDLAは以下の試験概要を公表しています。
| 試験時間 | 120分 |
| 120分 | 多肢選択式・100問程度 |
| 試験会場 | 各地の指定試験会場にて受験可能。申し込み時に、希望会場を選択する。 |
| 出題範囲 | シラバスより、JDLA認定プログラム修了レベルの出題 |
| 受験費用 | 一般:33,000円(税込)、学生:22,000円(税込)、会員:27,500円(税込) |
試験日程
E資格試験は、年に2回、2月中旬と8月下旬に実施されています。
2023年現在、次回のE資格試験は、
・「2024#1」であり、2024年2月16日(金)・17日(土)・18日(日)の3日間から選択することができます。
・じっくり準備をしたいという人は、2024年8月30日(金)・31日(土)・9月1日(日)に実施される「2024#2」を目標にしても良いでしょう。
試験の申し込みは約二か月半前から始まり、2月試験は12月1日午前9時から、8月試験は6月1日午前9時から開始されます。
申し込み自体は受験日前日の午後11時59分まで可能ですが、予約は先着順なので、希望の会場や時間帯がある場合はできる限り早めに予約することが大切です。
合格発表は、2月試験が3月頃、8月試験では9月頃になります。数週間から一か月ほどで結果がわかると考えて良いでしょう。
会場は多い
E資格試験の会場は、かなりの数が用意されており、少ない県でも2カ所、主要都市では10か所以上もあります。
パソコンを使う試験であることから、街のパソコン教室なども会場になっているようです。
会場数が多いため、自宅から行ける範囲の会場がすべて埋まってしまって試験が受けられないということはあまりないかもしれません。ただし、行きたい会場がある場合は早めに予約したほうが安心でしょう。
セキュリティが厳しい
E資格試験は、試験内容の漏洩やカンニングを防ぐため、受験者に対し厳重なチェックを行います。当日の雰囲気に圧倒されないようにしっかりとイメージしておきましょう。
受付は、15分前までに済ませます。受付では、本人確認書類2点の提示を求められます。運転免許証やパスポートなど政府発行の顔写真付き本人確認書類を持っていない人は早めに準備しておきましょう。
カメラで顔を撮影した後、電子署名をします。E資格試験の出題内容は、一切他言してはならないことになっており、試験開始前に秘密保持同意書の記入を求められます。
また、私物についても厳重なルールが適用されています。座席に持ち込めるものは、本人確認書類(ケースなどから外す)、ロッカーキー、眼鏡、マスクのみであり、その他の私物はロッカーに保管します。
一度受付してしまうと参考書なども閲覧できないため、早めに行きすぎると座って待つだけの時間が長くなってしまいます。その後、時間が来るとパソコンがある部屋に入ります。このとき眼鏡のチェックがあります。
問題数が多く時間はタイト
E資格試験では、100問前後の問題を120分で解かなければならないため、時間はタイトです。
残念ながら不合格だった人のなかには、最初からじっくり問題を解きすぎて、後半時間不足になってしまったという人は少なくありません。
そのため、試験本番は、解けそうな問題からどんどん解いていき、わからない問題は後回しにした方が失敗が少ないといわれています。
問題はパソコン上で、持ち込みは禁止
問題はパソコンの画面上で解きます。筆記用具や紙の持ち込みはできませんが、試験中は、ホワイトボードとペンを貸してもらえるので、計算式の途中メモなどに使うことができます。
電卓は、パソコンの画面上に表示されるものが使えますが、四則演算ができるだけの一般的なものとなっており、活用する機会はあまりなさそうです。
一通り回答が終わると、「回答済み問題/未回答問題/あとから見直す問題」を一覧でチェックすることができます。飛ばした問題や見直したい問題に戻ることもできます。
E資格の出題範囲
出題範囲は、応用数学、機械学習、深層学習、開発・運用環境の4科目であり、深層学習の出題が一番多くなっています。
・高校~大学レベルの基礎的な数学の知識や、
・ディープラーニングやディープラーニング以外の機械学習の知識、
・エッジコンピューティングなどの開発環境についての知識、
・PyTorchまたはTensorFlowを利用したプログラム実装に関する知識が求められます。
以上のように、E資格試験で出題される内容は、大きく分類すると以下の4つです。
①既存のAIの仕組みや手法を正しく理解しているかを問う問題
AIに関する知識問題です。AI技術が進化するなかで、さまざまなアルゴリズムが生まれました。それらの違いやメリット・デメリットを正しく理解し、改善できるロジックについて説明できるようにしましょう。
②数式の意味を理解しているかを問う問題
なぜその数式が重要なのか、数式自体の意味を理解していることが大切です。文系出身の人は、長い数式を見ると難しく感じてしまうものですが、学習率や勾配のイメージをしっかりと理解することで、必要な数式の形がおのずとわかるようになります。重要な数式と、そのロジックを理解しておきましょう。
③Pythonで表現したものを読み解く問題
E資格試験の目的は、プログラムを実装できるAIエンジニアを育成することにあります。前提となる知識をもとに、数式をあてはめ、それをPythonで書けるようになることが大切です。
④数式を計算できるか問う問題
計算問題です。良く問われる手計算の出題傾向は決まっているので、狙われやすい範囲をよく練習しておくことでクリアできるでしょう。ただし、近年は計算問題の出題は少なくなっています。
試験当日に焦らないための準備が重要

E資格試験には過去問が存在せず、教材も少ないため、実際の試験を想定した訓練が積みにくい資格試験です。
しっかりと知識が身に付いていても、出題傾向や問題の特徴がわかっていなければ点数には結びつきません。
ここでは、「試験当日に強い」E資格対策講座を紹介します。
【AI研究所】「E資格対策ディープラーニング短期集中講座」
「E資格対策ディープラーニング短期集中講座」は、JDLA認定プログラムのひとつであり、修了すればE資格の受験資格が得られます。
また、E資格試験に合格するために必要な知識が短期間でしっかりと身に付くという点で注目を集めています。
「E資格対策ディープラーニング短期集中講座」では、週に一回の講義が4回分の構成になっており、一か月でE資格に必要な知識を全て網羅できます。
もちろん確実に合格を目指すためには、講義以外にも自習の時間を確保することが大切ですが、重要な箇所だけ濃縮した、クオリティの高い講義を受けることには大きな意味があります。効率の良い勉強を進めたい人に向いている講座でしょう。
「E資格対策ディープラーニング短期集中講座」は、なぜ本番に強いといわれているのでしょうか。
教材が充実している
多くの受講者から好評を得ているのが、「教材の充実度」です。
全572ページに渡るオリジナル教材「E資格完全攻略テキストブック」や「丸暗記ブック」など、自習にも役立つテキストや問題集が配布されます。
講義や問題集のなかで詳しく解説している箇所が、実際の試験でも出題されたという声が多く聞かれており、教材のクオリティの高さには定評があります。「丸暗記ブック」は試験直前の最終チェックにも役立ったという声が多く聞かれています。
直前対策や模試が受けられる
「E資格対策ディープラーニング短期集中講座」には、試験直前フォローアップ講座 + 模擬試験が付属しています。
フォローアップ講座では、講義の内容の総復習や過去の出題傾向をもとに作成された問題演習に取り組みながら、模擬試験の正答率70%を目指します。
模擬試験は、実際の試験を想定した全119問で構成されており、試験中の時間配分などにも慣れることができます。
講義や講師の質が高い
「E資格対策ディープラーニング短期集中講座」を実施するAI研究所は、株式会社VOSTによって運営されています。
株式会社VOSTは、AIをはじめとしたさまざまな技術を社会に実装すべく、技術コンサルタント事業をメインに展開する会社です。
そのため、講義のわかりやすさや教材のクオリティにこだわりぬき、講師は現役のAIエンジニアのなかからわかりやすい説明を得意とする人材を厳選しています。
本業でAIを扱っている会社ですから、講義や講師の質はどこにも負けない自信を持っています。
手厚いサポート体制
ただ講義を聴くだけでなく、万全のサポート体制も「E資格対策ディープラーニング短期集中講座」の魅力です。
学習を進めるなかでわからないことがあったり、試験対策に不安があったりした場合は、個別に講師に質問・相談することができます。
これは本講義/オンライン講義/eラーニング共通であり、合格までしっかりとサポートする体制を構築しています。
こうした手厚いサポートにより、AIに関して初心者であっても、合格レベルの知識が身に付きます。挫折率の高いE資格対策講座のなかでは、驚異の修了率99.2%を誇っています。
試験日までにしっかりと準備を整え、E資格合格を目指そう
E資格は、難易度も高く、簡単に合格できる資格ではありません。しかし、丁寧な学習と質の高いサポートがあれば、合格を勝ち取ることは不可能ではありません。
試験の内容や出題傾向をしっかりと分析し、効率的な学習を目指しましょう。